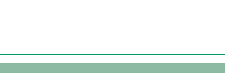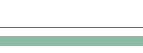ライフスタイル総合研究所TOP
文化とその周辺
●奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」4 
●奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」3 
●奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」2 
●奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」1 
●芸術融合の世界「伝統芸能の響」4 
●芸術融合の世界「伝統芸能の響」3 
●芸術融合の世界「伝統芸能の響」2 
●芸術融合の世界「伝統芸能の響」1 
●第二十七回「八ヶ岳薪能」4 
●第二十七回「八ヶ岳薪能」3 
●第二十七回「八ヶ岳薪能」2 
●第二十七回「八ヶ岳薪能」1 
●奉納 第二十六回「八ヶ岳薪能」 
●伝統と文化「能と狂言」3 
●奉納 第二十五回「八ヶ岳薪能」身曾岐神社 
●伝統と文化「能と狂言」2 
●伝統と文化「能と狂言」1 
●「空海」 
●八ヶ岳「平和への祈り」コンサート 
●奉納 第二十四回「八ヶ岳薪能」 
●八ヶ岳特別舞踊公演「伝統芸能の今2014」 
●身曾岐神社 究極の開運法「初学修行座」1泊2日 
●身曾岐神社「究極の開運法」弐 
●身曾岐神社「究極の開運法」壱 
●八ヶ岳「平和への祈り」コンサート ♪神域から世界に向けて♪ 
●奉納 第二十三回「八ヶ岳薪能」 
●伝統芸能の今2012 
●奉納 第二十二回「八ヶ岳薪能」 
●八ヶ岳「平和への祈り」コンサート 
●神社の屋根 
●第3回芸能セミナー「舞台化粧の魅力を探る」 
●奉納 第二十一回 八ヶ岳薪能 
●奉納 第21回「八ヶ岳薪能」東日本大震災 復興支援公演 
●第2回芸能セミナー「歌舞伎音楽 常磐津のルーツと演奏」 
●黒澤明生誕100年祭 IN 北杜市 薪能 「白田村」 
●黒澤明生誕100年祭 IN 北杜市 薪能 「マクベス」 
●能について 
●奉納 第二十回記念「八ヶ岳薪能」 
●御柱祭 
●「伝統文化こども教室」事業継続要望署名のお願い 
●2009年「八ヶ岳薪能」 
●第十七回「八ヶ岳薪能」 
●夢黄櫨染 
●2007年「八ヶ岳薪能」身曾岐神社 能楽殿 
●2006年「八ヶ岳薪能」 
●花押 心を映す鑑 
●西洋暦と旧暦 
●伝統芸能を楽しむつどい 
●2005年「八ヶ岳薪能」満天の星空の下、神池に浮かぶ幽玄の世界? 
奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」4
投稿日:2018年06月12日 09:00
◆奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」 神事 清秡の儀 宮司 坂田安儀 解説 能楽評論家 増田正造 能 宝生和英 高砂 狂言 文荷 野村萬斎 神事 篝火点火の儀 神職 能 辰巳満次…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」3
投稿日:2018年06月07日 09:00
■能 邯鄲 かんたん 辰巳満次郎 辰巳満次郎のDVD、『能M-1「邯鄲」傘之出』は、正倉院の箜篌(くご)を再現した音楽と共に、新しい時代を告げた。宝生流はきびしく古格を守りつつも、常に先端を切っている…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」2
投稿日:2018年05月28日 09:00
■狂言 文荷 ふみにない 野村萬斎 中世は男色流行の時代。稚児へのラブレターを主人に託された太郎冠者と次郎冠者。竹杖の真ん中にぶら下げて二人で担いでいくが、なんとも重い。二人が内緒で文を開けてみると「…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十八回「八ヶ岳薪能」1
投稿日:2018年05月24日 09:00
■能 高砂 たかさご 宝生和英 「高砂や。この浦船に帆をあげて。月もろともに出で潮の」。落語にも扱われ、もっとも有名な謡である。阿蘇の宮の神主が海を隔てての夫婦松を訪れるため、高砂から新造船に乗って住…続きを読む
この記事へのコメント (0)
芸術融合の世界「伝統芸能の響」4
投稿日:2017年11月09日 09:00
◆芸術融合の世界「伝統芸能の響」 開催日:平成29年11月15日(水曜日)開場13:30 開演14:00-16:30頃終演予定 会 場:国立能楽堂 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-18-1 JR総武線「千駄ヶ…続きを読む
この記事へのコメント (0)
芸術融合の世界「伝統芸能の響」3
投稿日:2017年11月03日 09:00
■日本舞踊 月の猩猩 藤舎呂悦作調 のびやかな囃子に引かれて浮かび出た酒好きな妖精・猩々は、波の音を鼓として舞を舞います。酌めども尽きる事の無い酒壺を与えられ「乱」となり、音楽も次第に至難な技術の秘曲…続きを読む
この記事へのコメント (0)
芸術融合の世界「伝統芸能の響」2
投稿日:2017年10月27日 09:00
■狂言 柿山伏 柿を無断で食べている山伏を見つけた畑主。梢に隠れた山伏を何とか懲らしめようと・・・ 山伏 野村太一郎、畑主 月崎晴夫、後見 竹山悠樹 ■長唄 鶴亀 中国・唐の時代、新年を祝う節会が開か…続きを読む
この記事へのコメント (0)
芸術融合の世界「伝統芸能の響」1
投稿日:2017年10月23日 09:00
■国際文化交流事業 日本と中東諸国の文化交流を目指して、「檜の会」は国際社会の中で益々国際文化交流を活発化し、自国の文化を世界に伝え、同時に海外の文化を学び、次世代に伝承するという役割を担っております…続きを読む
この記事へのコメント (0)
第二十七回「八ヶ岳薪能」4
投稿日:2017年06月18日 09:00
◆奉納 第二十七回「八ヶ岳薪能」 神事 清祓の儀 宮司 坂田安儀 解説 能楽評論家 増田正造 能 巻絹 辰巳満次郎 狂言 二人大名 野村萬斎 神事 篝火点火の儀 神職 能 小…続きを読む
この記事へのコメント (0)
第二十七回「八ヶ岳薪能」3
投稿日:2017年06月09日 09:00
■能 小鍛冶 白頭 こかじ 宝生和英 世の中、なにが潔いかというと、刀鍛冶こそがその筆頭であろう。天子の見た霊夢によって剣を打てという勅命が、三条の小鍛冶宗近に下る。我に劣らぬ相槌がいないと断るが、も…続きを読む
この記事へのコメント (0)
第二十七回「八ヶ岳薪能」2
投稿日:2017年06月01日 09:00
■狂言 二人大名 ふたりだいみょう 野村萬斎 都へ上る大名が、友人の大名を誘って出かけるが、家来を連れず自身で太刀を持っているので、だれか通りがかりの者がいないかと待つところに、急ぎの使いの者がやって…続きを読む
この記事へのコメント (0)
第二十七回「八ヶ岳薪能」1
投稿日:2017年05月27日 09:00
■能 巻絹 まきぎぬ 辰巳満次郎 巻絹とは軸に巻き付けた絹の反物。これを千本、紀伊の国の熊野三社権現に奉納せよとの勅命。都からの使いが到着しない。彼は本宮に着く前に、音無の天神に参詣し、梅の香りに引か…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十六回「八ヶ岳薪能」
投稿日:2016年06月27日 09:00
■能 吉野天人 よしのてんにん 角幸二郎 花の吉野山。訪れた都人たちの前に里の女が現れ、共に桜を楽しみ、花に魅かれた天人と告げて消え失せる前段。「その古(いにしえ)の五節の舞。小忌(おみ)の衣の羽袖を…続きを読む
この記事へのコメント (0)
伝統と文化「能と狂言」3
投稿日:2015年07月28日 09:00
◆伝承 650年もの間、脈々と親から子へ、子から孫へ、また、師匠から弟子へと 一度も絶えることなく伝え続けている演劇は、世界中でも日本の能や狂言が 唯一であると言っても過言ではないでしょう。 能楽は、…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十五回「八ヶ岳薪能」身曾岐神社
投稿日:2015年06月24日 09:00
■能 天鼓 てんこ 悲しく美しい能である。後漢の時代。天から鼓が降ると夢見て懐妊し、生 まれた少年。天鼓と名付けられ、事実天から鼓が降り妙音を発した。取り上 げようとした皇帝の命に従わず山に隠れたが、…続きを読む
この記事へのコメント (0)
伝統と文化「能と狂言」2
投稿日:2015年06月22日 09:00
■能:夢の一時の物語 能は演劇です。しかも現代でもその基本の形をほとんど変えずに、また時 代時代に対応しながら伝承されている、世界で一番古い舞台芸術なのです。 能の物語はおよそ250話あります。そして…続きを読む
この記事へのコメント (0)
伝統と文化「能と狂言」1
投稿日:2015年05月22日 09:00
◆能の歴史 六世紀中頃、中国から「雅楽」が上陸して、また、中国の様々な民間芸能 も流れ込んで、それらは「散楽」と呼ばれました。今も宮内庁に受け継がれ ている「雅楽」といろいろな芸や技を寄せ集め演じられ…続きを読む
この記事へのコメント (0)
「空海」
投稿日:2015年02月18日 09:00
空海は宝亀5年(774年)に讃岐国多度郡屏風浦、現在の香川県善通寺市 で生まれました。真言宗の伝承では空海の誕生日を6月15日としていますが、 これは中国密教の大成者である不空三蔵の入滅の日であり、空…続きを読む
この記事へのコメント (0)
八ヶ岳「平和への祈り」コンサート
投稿日:2014年07月25日 09:00
雅楽師、ヴァイオリニスト、アコーディオニストの三人が共に音楽を奏で ることを、誰が想像できたでしょう!それは昨年のことでした。東洋と西洋、 歴史と文化を超えて三つの楽器が奇跡の出会いを果たしました。 …続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十四回「八ヶ岳薪能」
投稿日:2014年06月24日 09:00
■能 橋弁慶 弦師 はしべんけい 弁慶(シテ)は宿敵のため夜毎五条の天神に参詣している。供の家来(ト モ)から不思議な少年が飛鳥のごとく人を斬ると聞いて思いとどまろうとす るが、弁慶ほどのものが無念と…続きを読む
この記事へのコメント (0)
八ヶ岳特別舞踊公演「伝統芸能の今2014」
投稿日:2014年04月28日 17:00
★ゴールドリボン+世界の子どもにワクチンをチャリティー企画 伝統芸能を気軽にご覧いただきながら、チャリティーに参加していただく というこの公演は2009年よりスタートし、今年で6年目を迎えます。今回…続きを読む
この記事へのコメント (0)
身曾岐神社 究極の開運法「初学修行座」1泊2日
投稿日:2014年02月25日 17:00
◆身曾岐神社 究極の開運法「初学修行座」1泊2日 修行内容:聴聞(神学講話)、息吹永世(静体呼吸行)、祓座(言霊祓行) 開催日:2014年3月8日(土曜日) 9:00神社集合、10:00開始 …続きを読む
この記事へのコメント (0)
身曾岐神社「究極の開運法」弐
投稿日:2014年02月25日 09:00
■初学修行座の4つの柱 祓座:息の行。聴聞:日本の精神伝統文化を学ぶ。食事:食べものによっ て身体はでき、食べ方によって運命が定まる。清掃:おそうじもみそぎに通 じます。 ■食 優れた医者でもあった御…続きを読む
この記事へのコメント (0)
身曾岐神社「究極の開運法」壱
投稿日:2014年01月29日 17:00
身曾岐神社では、日本人の精神文化の源流である古神道の奥義を受け継ぎ、 みなさまに広くお伝えしております。神世から明治維新にいたる千古のあい だ、歴朝の宮中祭祀を司ってきた神祇伯に連綿と受け継がれ、今日…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十三回「八ヶ岳薪能」
投稿日:2013年07月25日 11:30
■能 井筒 いづつ 今年は能の大成者世阿弥の生誕六百五十年に当たる。父観阿弥と共に日本 の文化に演劇を加えた偉人である。それを記念して今年の八ヶ岳薪能には、 世阿弥最高傑作の「井筒」を艶麗無比の金剛…続きを読む
この記事へのコメント (0)
八ヶ岳「平和への祈り」コンサート ♪神域から世界に向けて♪
投稿日:2013年07月25日 11:30
2013年、雅楽師・東儀秀樹とヴァイオリニスト・古澤巌の全国ツアーは、 アコーディオンのイメージを大きく変え、世界の音楽シーンで活躍を続ける cobaを迎え、新たな地平を切り開きます。 雅楽の東儀…続きを読む
この記事へのコメント (0)
伝統芸能の今2012
投稿日:2012年08月28日 09:00
■源平双乱「六道の辻」 この世とあの世の境界である「六道の辻」。ここへやってきたのは、金の 亡者と悪名高い平家の武士(茂山逸平)。なんとか地獄行きを逃れたいものだ と頭を悩ませています。そこへ、武勇…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十二回「八ヶ岳薪能」
投稿日:2012年07月27日 09:00
■能 俊寛 しゅんかん 観世清和 平家打倒のクーデター計画が漏れ、鬼界島に流された三人。硫黄の燃える 鬼が済むような薩摩潟の孤島である。首謀者の息子である丹波少尉成経と、 平判官康頼は、信心する熊野…続きを読む
この記事へのコメント (0)
八ヶ岳「平和への祈り」コンサート
投稿日:2012年07月20日 09:00
雅楽師・東儀秀樹とヴァイアリニスト・古澤巌は、十数年前、東儀の名曲 『午後の汀』をきっかけに出会い、これまで全国ツアーを始め、数多くのコ ンサートを行って来ました。型破りな二人はさまざまなジャンルの…続きを読む
この記事へのコメント (0)
神社の屋根
投稿日:2012年04月27日 13:25
伊勢神宮は来年、平成25年に第62回の遷宮が行われます。持統天皇の時代から約20年ごとに行われ、1300年余りの長きに亘って連綿と続けられてきた行事は世界でも類例がありません。式年とは定まった年という…続きを読む
この記事へのコメント (0)
第3回芸能セミナー「舞台化粧の魅力を探る」
投稿日:2011年09月08日 09:00
第3回芸能セミナー「舞台化粧の魅力を探る」 講師 舞台化粧司 小池希英 氏 歌舞伎や日本舞踊の白塗りの化粧は特殊なメーキャップとして知られてい ます。普段は拝…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十一回 八ヶ岳薪能
投稿日:2011年07月20日 09:00
「奉納 第二十一回 八ヶ岳薪能」 東日本大震災 復興支援公演 ■能 経正 替之型 上田公威 上田公威は、神戸能楽の名門上田家四兄弟の三番目。1963年生まれ。観世 宗家直門の気鋭のシテ方。 ■狂言…続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第21回「八ヶ岳薪能」東日本大震災 復興支援公演
投稿日:2011年06月22日 09:00
神事 清祓の儀 宮司 坂田安儀 解説 能楽評論家 増田正造 能 経正 替之型 上田公威 狂言 柿山伏 野村萬斎 神事 篝火点火の儀 神 職 日 時:平成23年8月3日(…続きを読む
この記事へのコメント (0)
第2回芸能セミナー「歌舞伎音楽 常磐津のルーツと演奏」
投稿日:2011年05月27日 14:26
第2回芸能セミナー「歌舞伎音楽 常磐津のルーツと演奏」 講師 常磐津都史 氏 常磐津は歌舞伎音楽の中で、歴史・伝記・人情物と幅広く、その描写は分 か…続きを読む
この記事へのコメント (0)
黒澤明生誕100年祭 IN 北杜市 薪能 「白田村」
投稿日:2010年09月15日 09:00
黒澤明生誕100年祭 IN 北杜市 薪能 「白田村」 解 説 黒澤明監督の能 増田 正造(能楽評論家) 上 映 八島 黒澤明監督未公開映像 狂言語り 那須 …続きを読む
この記事へのコメント (0)
黒澤明生誕100年祭 IN 北杜市 薪能 「マクベス」
投稿日:2010年09月13日 09:00
黒澤明生誕100年祭 IN 北杜市 薪能 「マクベス」 解 説 蜘蛛巣城と能 増田 正造(能楽評論家) 上 映 八島 黒澤明監督未公開映像 能 舞 人間五十年 作曲:玄祥梅…続きを読む
この記事へのコメント (0)
能について
投稿日:2010年09月10日 09:00
■能 能楽堂で演じられるいろいろな「能」をご覧になったり、あるいは、テレ ビで観ていらっしゃる方は多いと思います。能には、 ・能面、能装束などの美術的側面 ・謡の旋律や囃子のリズムなどの音楽的側面 …続きを読む
この記事へのコメント (0)
奉納 第二十回記念「八ヶ岳薪能」
投稿日:2010年06月25日 16:29
能「翁」おきな 翁の成立は能よりずっと古い。「能にして能にあらず」とも、「翁こそが 能である」とされる。 鏡の間にはご神体として翁面が飾られ、一同ご神酒をいただいて出る。地 謡と囃子方も、侍烏帽子…続きを読む
この記事へのコメント (0)
御柱祭
投稿日:2010年03月26日 15:05
御柱について信州・諏訪大社では七年に一度の寅と申の年に宝殿を新築し、 社殿の四隅にあるモミの大木を建て替える祭りを行います。この祭りを「式 年造営御柱大祭」、通称「御柱祭」と呼び、諏訪地方の6市町村…続きを読む
この記事へのコメント (0)
「伝統文化こども教室」事業継続要望署名のお願い
投稿日:2009年11月27日 13:21
この度の政権交代に伴ない、民主党の行っている事業仕分けにより、「伝 統文化こども教室」の事業が廃止となりました。私共は設立から五期目を向 かえますが、日本人のアイデンティティを伝統文化から育む事を大…続きを読む
この記事へのコメント (0)
2009年「八ヶ岳薪能」
投稿日:2009年07月17日 09:00
全国200ヵ所以上で行われ、今や夏の風物詩としてすっかり定着した観の ある薪能。漆黒の闇に燃えるかがり火の炎が、演者と舞台をほのかに照らし、 見る者を幽玄の世界へと誘います。 身曾岐神社で毎年8月…続きを読む
この記事へのコメント (0)
第十七回「八ヶ岳薪能」
投稿日:2007年07月30日 09:35
■能 清経 きよつね 世阿弥の描く滅びの美学。傾く平家の運命、雑兵(ぞうひょう)に討たれる不名誉を避けるために、この貴公子は、入水して極楽への道を選んだ。 父・清盛の暴虐が止まぬならわが命をと薬を…続きを読む
この記事へのコメント (0)
夢黄櫨染
投稿日:2007年07月17日 10:55
平成二年の夏、国学院大学の協力を得て、歴代天皇の装束が残されている京都の広隆寺に調査に行ったときのことです。暗い部屋の中を懐中電灯で照らしていたとき、不用意に落としてしまった懐中電灯を拾おうとして、…続きを読む
この記事へのコメント (0)
2007年「八ヶ岳薪能」身曾岐神社 能楽殿
投稿日:2007年07月04日 09:40
テーマ:2007年「八ヶ岳薪能」 神事 舞台清め祓い式 宮司 坂田 安儀 解説 能楽評論家 増田 正造 能 清経 塩津 哲生 狂…続きを読む
この記事へのコメント (0)
2006年「八ヶ岳薪能」
投稿日:2006年07月01日 14:56
全国200ヵ所以上で行われ、今や夏の風物詩としてすっかり定着した観のある薪能。漆黒の闇に燃えるかがり火の炎が、演者と舞台をほのかに照らし、見る者を幽玄の世界へと誘います。 中でもこの身曾岐神社で毎…続きを読む
この記事へのコメント (0)
花押 心を映す鑑
投稿日:2006年05月18日 10:49
人の歴史になくてはならないものに言葉と文字があります。この世に生を受けたとき、ご両親から授けられた数々の期待と夢を託した貴重なお名前があります。一人の人間としての価値が託されている名前の意義、それを…続きを読む
この記事へのコメント (0)
西洋暦と旧暦
投稿日:2006年01月15日 22:13
現在私たちが使っているのはグレゴリオ暦という西洋暦です。明治の最初に脱亜入欧のために、それまで使われてきた日本の暦を無理矢理捨て去って採用したものです。 その時まで使っていた暦は天保暦というもので…続きを読む
この記事へのコメント (0)
伝統芸能を楽しむつどい
投稿日:2005年11月16日 13:39
昭和58年に交通事故で2ヶ月入院しました。其の時から自分の人生が大きく変わったと思います。大阪万博の昭和45年に師匠と別れ一人立ちをしましたが、その頃から普通の舞踊家ではいてられなかったようです。…続きを読む
この記事へのコメント (0)
2005年「八ヶ岳薪能」満天の星空の下、神池に浮かぶ幽玄の世界?
投稿日:2005年05月18日 11:17
全国200ヵ所以上で行われ、今や夏の風物詩としてすっかり定着した観のある薪能。漆黒の闇に燃えるかがり火の炎が、演者と舞台をほのかに照らし、見る者を幽玄の世界へと誘います。 中でもこの身曾岐神社で毎…続きを読む
この記事へのコメント (0)
|